 |
| |
 |
[ 1. 皮膚に定着するマラセチア叢の解析 ] |
|
■培養法から非培養法へ
これまでにも皮膚マラセチアの菌叢解析は行われてきましたが、結果は研究者により大きく異なっていました[図4]。
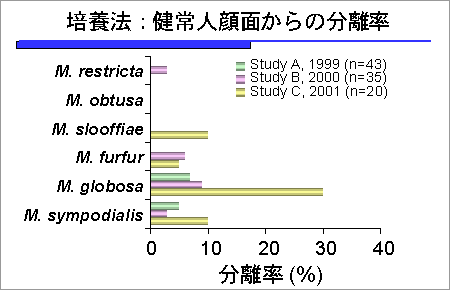 |
| 図4 |
|
例えば、Study A, B,
CのいずれにおいてもM. restrictaはほとんど分離されていません。一番分離率の高かった菌種で約30%です。マラセチア属には現在11菌種が知られていますが、中には培養困難な菌種が存在します。つまりこの差異は分離技術に起因すると考え、培養を介さない非培養検出法を新たに開発しました[図5]。
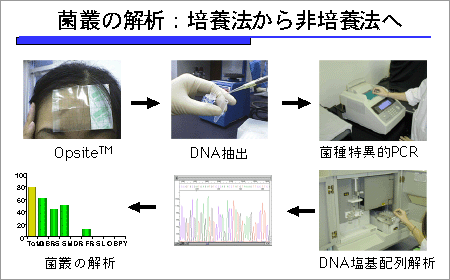 |
| 図5 |
|
これは、皮膚にテープを接着させ、そこから直接MalasseziaをPCR-DNAシーケンス法で検出するものです。精度は高いですが難点は、煩雑であることとです。
■アトピー性皮膚炎患者も健常人も菌叢は同じ
非培養法により解析した結果、M.
globosa/M. restrictaがほぼ全例から検出されました。ここが培養法の結果と著しくことなる点です。あまりの結果の解離に、当時は誰からも信じてもらえませんでした。意外(?)なことに、患者も健常人も菌叢はほぼ同一でした[図6]。
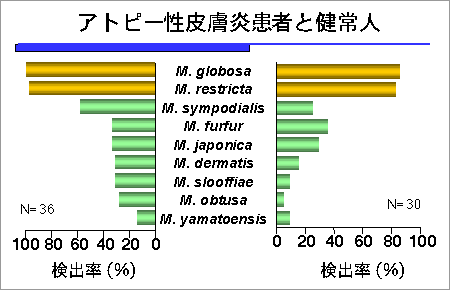 |
| 図6 |
|
菌叢解析の結果から、ADの増悪にはM.
globosa/M. restrictaのいずれか、あるいは両方の菌種が深く関与していると考えられました。
■遺伝子型は異なっていた
患者と健常人由来のM.
globosa/M. restrictaのIGSとよばれる領域のDNA塩基配列を解析したとこと、(CT)nおよび(GT)nの反復配列が存在していました。この繰り返し回数は、患者と健常人で異なっていました[図7]。
系統樹でみるとより明らかです[図8]。
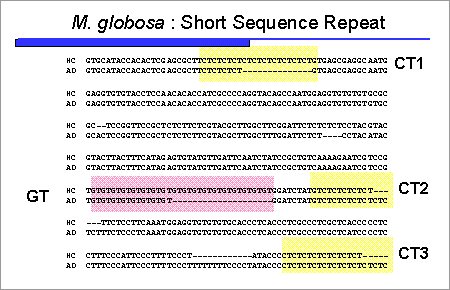 |
| 図7 |
|
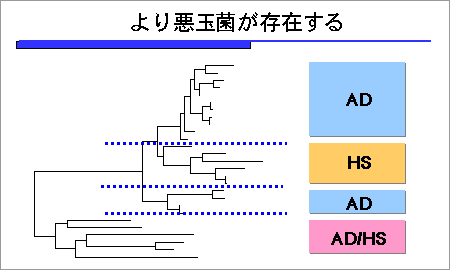 |
| 図8 |
|
このことから、特定の遺伝子型を有する菌株がより増悪に関与していると考えられました。微生物研究者は通常、患者と健常人の菌叢は異なることを期待します(その方が論文を書きやすいから)。しかし、期待に反したためこの実験の着想に至りました。おそらく菌叢が異なっていたらこの実験は行わなかったでしょう。
|
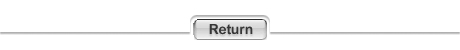 |
|
|
|
|
|
|